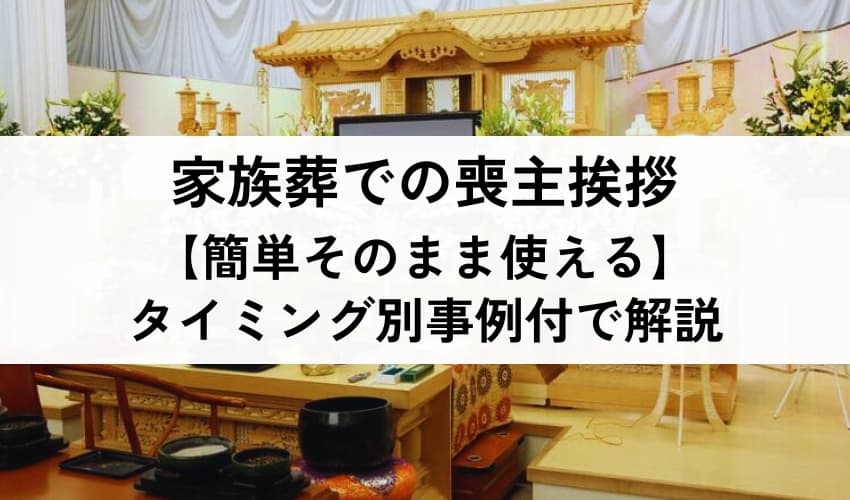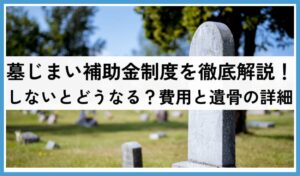家族葬という親しい人たちだけで行う小規模な葬儀で、喪主としての挨拶はどのように行うのが適切なのでしょうか?
多くの方が、家族葬の喪主挨拶にはどのような特徴があるのか、また、どのタイミングでどのような言葉を選ぶべきなのか、といった疑問を抱えていることでしょう。
この記事では、家族葬での喪主挨拶の基本から、具体的な事例までをわかりやすく解説していきます。
また、挨拶の際に気をつけたいポイントや、避けるべき表現なども詳しくお伝えしていきます。
家族葬での喪主挨拶に自信を持って取り組むためのヒントとして、ぜひ最後までお読みください。
- 家族葬は親しい人たちだけで行われるため、喪主の挨拶は参列者との絆を深める上で重要
- 喪主は故人との深い関係を伝えることが求められる
- 挨拶を通して故人への感謝と哀悼の気持ちを表す
- 挨拶では参列者への感謝の気持ちも伝える必要がある
- 挨拶の準備と練習が重要で、故人との思い出を交えることで共感を得やすい
家族葬での喪主挨拶の重要性を簡単に解説

家族葬は、親しい人たちだけで故人を偲ぶ場となります。
その中で、喪主としての挨拶は非常に重要な役割を果たします。
挨拶を通じて、故人への感謝や哀悼の気持ちを伝えるとともに、参列者との絆を深めることができます。
家族葬の特性と喪主の役割
家族葬は、規模が小さく、より身内や親しい人たち向けのものです。
その特性から、喪主としての役割は非常に重要となります。
喪主は、故人との関係を深く伝えることが求められるだけでなく、参列者との距離が近いため、心のこもった挨拶が期待されます。
家族葬の場では、喪主の挨拶が故人と参列者を繋ぐ大切な役割を果たします。
そのため、喪主としての挨拶には、故人への感謝や哀悼の気持ち、そして参列者への感謝の気持ちをしっかりと込めることが大切です。
また、家族葬の特性を理解し、その上での挨拶が求められるため、事前の準備や練習も欠かせません。
簡単に心掛けたい喪主挨拶の基本ポイント
喪主としての挨拶は、故人への感謝や哀悼の気持ちを伝えることが最も重要です。
その一方で、家族葬の場では、参列者との距離が近いため、簡潔に、しかし深い感謝の気持ちを込めて伝えることがポイントとなります。
挨拶の際には、故人との思い出や、故人が生きていた時のエピソードを織り交ぜることで、参列者との共感を得やすくなります。
また、感謝の気持ちを具体的なエピソードや数字で示すことで、より伝わりやすくなります。
例えば、「故人とは20年以上の長い付き合いで、多くの思い出があります。
」などと伝えることで、その深い関係性を参列者に伝えることができます。
家族葬で喪主が挨拶をするタイミング
家族葬は、親しい人たちだけで故人を偲ぶ場として行われます。

喪主としての挨拶は、この特別な場での大切な役割となります。
一般的に、家族葬での喪主の挨拶は、葬儀の冒頭や最後に行われることが多いです。
挨拶の際には、故人との思い出や、参列者への感謝の言葉を述べることが一般的です。
また、故人が生前に残した言葉やエピソードを共有することで、参列者との絆を深めることができるでしょう。
挨拶の内容やタイミングは、故人や家族の意向を尊重しながら、最も適切な方法を選ぶことが大切です。
通夜の閉式
通夜の閉式は、故人を偲ぶ夜の儀式を終える際の重要な時間となります。
閉式では、参列者全員が故人の前で手を合わせ、最後のお別れの時間を持ちます。
この時、喪主や家族が簡潔な感謝の言葉を述べることも一般的です。
閉式の後、故人は次の日の告別式に備えて安置されます。
参列者は、この閉式をもって帰宅することが多いです。
通夜の閉式は、故人との最後の夜を静かに、そして心から偲ぶ大切な時間となります。
通夜の振る舞いの開式、閉式
通夜の振る舞いは、故人を偲ぶ儀式の中での一部として行われるものです。
開式では、参列者を迎え入れ、故人のための儀式の開始を告げる時間となります。
一方、閉式は、儀式の終了を示すものとなります。
振る舞いの際には、故人との関わりや思い出を共有することが多く、参列者との絆を深める機会となります。
開式や閉式の際には、喪主や家族が挨拶をすることもあります。
この挨拶は、故人への感謝や、参列者への感謝の言葉を伝える大切な時間となります。
告別式・出棺
告別式は、故人との最後のお別れの時間となります。
この儀式の中で、参列者は一人ひとりが故人の前に進み、手を合わせて最後の別れを告げます。
出棺は、告別式の後に行われ、故人が棺桶に安置され、葬儀場や家から出て行く際の儀式となります。
この時、喪主や家族は、故人を見送るとともに、参列者に感謝の言葉を述べることが一般的です。
告別式や出棺は、故人との最後の時間を大切にし、心からの感謝とお別れを伝える重要な儀式となります。
精進落とし
精進落としは、葬儀や法事が終了した後に行われる食事会のことを指します。
この名前は、葬儀や法事での精進料理から通常の食事へと移行することを意味しており、故人の死を受け入れ、日常へと戻る過程を象徴しています。
遺族や参列者が一堂に会し、故人の思い出を語り合いながら食事を共にすることで、故人への感謝や追悼の意を示します。
また、喪主や遺族が主催するこの食事会は、参列者への感謝の気持ちを伝える大切な場ともなっています。
故人との最後のお別れの場として、また新たな日常への一歩として、精進落としは多くの人々にとって欠かせない儀式となっています。
喪主挨拶のコツとマナーを簡単に解説

喪主としての挨拶は、故人を偲ぶ場として非常に重要な役割を果たします。
そのため、いくつかの基本的なコツやマナーを知っておくことで、より心に響く挨拶を行うことができるでしょう。
まず、故人との関係や共有した思い出を具体的に述べることで、参列者との共感を生むことができます。
また、喪主としての感謝の気持ちや哀悼の意をしっかりと伝えることが大切です。
一方、過度な感情の表現や長過ぎる挨拶は避けるよう心掛けましょう。
挨拶の際には、故人との関係やエピソードを交えながら、心からの感謝の言葉を述べることが求められます。
このように、喪主としての挨拶には、故人を偲ぶ心のこもった言葉と、参列者への感謝の気持ちをしっかりと伝えることが大切です。
感謝の気持ちを伝える
故人との思い出や、参列者への感謝の気持ちを伝える際には、具体的なエピソードや瞬間を思い返すことで、より深い感謝の気持ちを伝えることができます。
例えば、故人と過ごした特別な日や、故人から学んだこと、または故人との間に生まれた絆などを挨拶の中で述べることで、参列者との共感を生むことができるでしょう。
また、参列者への感謝の言葉も忘れずに伝えることが大切です。
彼らがこの場に集まってくれたこと、故人を偲ぶ気持ちを共有してくれることへの感謝を、心からの言葉で伝えることが重要です。
無理に個性を出さない
挨拶は、故人を偲ぶ場としての役割を果たすものです。
そのため、無理に自分の個性を前面に出す必要はありません。
心のこもった言葉を選ぶことが大切です。
しかし、それは自分らしさを完全に抑えるという意味ではありません。
故人との関係や共有した思い出を語る際に、自分らしい言葉で伝えることができれば、それが最も心に響く挨拶となるでしょう。
大切なのは、故人や参列者に対する敬意を忘れず、心からの言葉で感謝の気持ちを伝えることです。
避けるべき表現に注意
喪主としての挨拶には、避けるべき表現があります。
家族葬での喪主挨拶は、故人との関係や思い出を共有する大切な時間です。
そのため、不適切な言葉や表現を使うことで、参列者に不快な思いをさせてしまう可能性があります。
例えば、過度にネガティブな言葉や、他者を批判するような言葉は避けるべきです。
また、故人の私事や家族の内情を詳しく話すことも控えるべきでしょう。
後述の「家族葬で喪主挨拶で避けるべき表現」で、具体的な避けるべき表現や注意点について詳しく解説いたします。
喪主としての挨拶は、故人への敬意と感謝の気持ちを伝える大切な時間ですので、心を込めて、適切な言葉を選ぶことが大切です。
喪主挨拶の所要時間
挨拶の時間は、短すぎず長すぎない、適切な長さを心掛けることが大切です。
一般的には、3分から5分程度が適切とされています。
しかし、この時間はあくまで目安であり、故人との関係や共有したい内容によって変わることがあります。
喪主としての挨拶は、故人への感謝や思い出を共有する時間ですので、焦らず、自分のペースで話すことが大切です。
ただし、あまりにも長くなり過ぎると、参列者が疲れてしまう可能性もあるため、適切なバランスを取ることが求められます。
挨拶の際の声のトーン:ゆっくり簡単に
挨拶の際の声のトーンは、ゆっくりと落ち着いたものが好ましいです。
また、簡潔に、しかし感情を込めて伝えることが大切です。
喪主挨拶は、故人への感謝や思い出を伝える大切な時間です。
そのため、焦らず、自分のペースで、心を込めて話すことが重要です。
また、原稿を読む際には、あまりにも原稿に頼り過ぎると、自然な感情が伝わりにくくなるため、適度に目を上げて参列者と目を合わせることが大切です。
挨拶の内容やトーンによって、故人への敬意や感謝の気持ちをしっかりと伝えることができます。
原稿を読みながらの挨拶でも良い?
原稿を読みながらの挨拶も問題ありません。
しかし、あまりにも原稿に頼り過ぎると、自然な感情が伝わりにくくなるため、適度に目を上げて参列者と目を合わせることが大切です。
喪主としての挨拶は、故人への感謝や思い出を伝える大切な時間です。
そのため、原稿を使う場合でも、心を込めて、感情を伝えることが重要です。
また、原稿を使うことで、忘れてしまいそうなポイントや大切なメッセージをしっかりと伝えることができます。
ただし、原稿を読む際には、自然な感情や声のトーンを意識することで、より感動的な挨拶にすることができるでしょう。
家族葬の喪主挨拶で避けるべき表現

家族葬の喪主挨拶では、故人を偲ぶ場としての格式やマナーを守ることが求められます。
挨拶の際には、避けるべき表現がいくつか存在します。
これらの表現を使用すると、不適切と受け取られる可能性が高まります。
例えば、過度な感謝や謝罪、過去の思い出ばかりを語ることは避けるべきです。
また、故人の死因や病気の詳細に触れることも控えるようにしましょう。
これらの情報は、家族葬の場においては不要であり、場の空気を悪くする可能性があります。
挨拶の際は、故人との思い出や、故人の人柄を中心に話すことで、参列者との共感を生むことができます。
また、故人を偲ぶ言葉を選ぶ際には、優しい口調で、感謝の気持ちを伝えることが大切です。
最後に、喪主としての挨拶は、故人を偲ぶ場としての格式を保ちつつ、心からの感謝の気持ちを伝えることが最も重要でしょう。
忌み言葉
忌み言葉とは、死や病気に関連する言葉のことを指します。
これらの言葉は、特定の文脈や場面での使用が避けられることが多いです。
例えば、「死」「病」などの言葉は、家族葬や葬儀の場では使用を控えることが推奨されます。
これは、故人や参列者の感情を逆なでする可能性があるためです。
また、これらの言葉は、不吉や悪いことを連想させるため、避けることが望ましいとされています。
挨拶の際には、故人を偲ぶ言葉や、感謝の気持ちを伝える言葉を選ぶことが大切です。
そして、忌み言葉を使用することなく、故人の思い出や人柄を中心に話すことで、参列者との共感を生むことができます。
重ね言葉
「永遠に」「ずっと」といった重ね言葉も、挨拶の際には適切ではありません。
繰り返しの表現は、故人を偲ぶ場としては適切でないとされています。
これは、過去の思い出や故人の存在を強調し過ぎると、参列者の心に重たさをもたらす可能性があるためです。
挨拶の際には、故人の思い出や人柄を中心に、簡潔かつ適切な言葉で表現することが求められます。
重ね言葉を使用することで、故人の存在を強調し過ぎることは避け、心からの感謝の気持ちを伝えることが大切です。
続き言葉
「そして」「また」といった続き言葉は、挨拶の際に使用するのは適切ではありません。
これらの言葉は、何かが続くことを示唆するもので、故人を偲ぶ場としては不適切とされています。
挨拶の際には、故人の思い出や、参列者との共有する想いを大切にする言葉を選ぶことが大切です。
例えば、「思い出す」「感謝する」といった言葉は、故人を偲ぶ場での挨拶として適切でしょう。
また、故人の生前のエピソードや、その人との思い出を共有することで、参列者との絆を深めることができます。
不吉な言葉
「不幸」「災難」といった不吉な言葉は、挨拶の際には適切ではありません。
これらの言葉は、故人や参列者に対して不適切と受け取られる可能性があります。
故人を偲ぶ場では、より穏やかで温かみのある言葉を選ぶことが推奨されます。
例えば、「旅立ち」「眠る」といった言葉は、故人の死を優しく表現することができます。
また、参列者の気持ちを考慮し、故人の思い出や功績を称える言葉を選ぶことで、故人を偲ぶ場をより心温まるものにすることができるでしょう。
直接的な言葉
「死亡」「亡くなる」といった直接的な言葉も、挨拶の際には適切ではありません。
故人を偲ぶ場としては、より優しい言葉を選ぶことが推奨されます。
例えば、「旅立ち」「眠る」といった言葉は、故人の死を優しく表現することができます。
また、故人の生前のエピソードや、その人との思い出を共有することで、参列者との絆を深めることができます。
挨拶の際には、故人の思い出や、参列者との共有する想いを大切にする言葉を選ぶことが大切です。
宗教的な表現
家族葬の場では、特定の宗教的な表現を避けることが推奨されます。
参列者の中には、異なる宗教の信者がいる可能性があるため、中立的な言葉を選ぶことが大切です。
例えば、キリスト教や仏教、イスラム教などの宗教に関連する言葉や祈りの言葉を使用するのは避けるべきです。
代わりに、故人の生前のエピソードや、その人との思い出を共有することで、参列者との絆を深めることができます。
挨拶の際には、故人の思い出や、参列者との共有する想いを大切にする言葉を選ぶことが大切です。
家族葬での喪主挨拶をタイミング別に簡単に解説

家族葬は、故人との最後のお別れの場として非常に大切な儀式です。
その中でも、喪主としての挨拶は、故人への感謝や参列者への感謝を伝える重要な役割を果たします。
しかし、挨拶のタイミングや内容には様々なバリエーションがあり、どのように挨拶をすればよいのか迷う方も多いでしょう。
ここでは、家族葬での喪主挨拶のタイミング別に、シンプルなものからエピソードを交えたものまで、さまざまな挨拶の例をご紹介いたします。
通夜から精進落としまで、それぞれの場面での挨拶のポイントや内容を理解し、故人への感謝の気持ちをしっかりと伝える手助けとしてお役立てください。
通夜閉式の挨拶例(シンプル)
- 今日は、故〇〇の通夜に足を運んでいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。
故人は、皆様との深い絆を感じながら、安らかに眠っていることでしょう。
皆様からの温かい支えに、心からの感謝を申し上げます。 明日の告別式は、午前〇時〇分から開始いたします。
お時間が許せば、ご参列いただけると幸いです。
重ねて、お礼申し上げます。 - 本日は、故〇〇を偲ぶ通夜にお越しいただき、深く感謝しております。
故人も、皆様の優しい心に包まれて、安心していることと信じております。
生前の故人へのご支援、ご愛情に、感謝の言葉も足りません。
明日の告別式は、午前〇時〇分からとなっております。
ご参加いただけますと幸いです。
改めて、ありがとうございました。 - 皆様、故〇〇の通夜に参列していただき、心からの感謝を申し上げます。
故人が皆様と過ごした日々を思い返し、感謝の気持ちを新たに感じております。
故人への温かい思い出や支えに、心より感謝申し上げます。
明朝の告別式は、午前〇時〇分に行われます。
お時間の許す限り、ご参列ください。
本日は、誠にありがとうございました。 - 今宵、故〇〇のためにお集まりいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。
故人は、皆様との深い絆を感じながら、安らかに眠っていることでしょう。
故人へのご愛情、ご支援に、深く感謝申し上げます。
明日の告別式は、午前〇時〇分からとなっております。
皆様のご参列を心よりお待ちしております。
重ねて、お礼申し上げます。 - 本日は、故〇〇の通夜にお越しいただき、心から感謝申し上げます。
故人が皆様と築いた絆を大切にし、彼の魂を偲びたいと思います。
皆様からの温かい言葉や支えに、心より感謝しております。
明日の告別式は、午前〇時〇分から開始いたします。
ご参列いただけると幸いです。
本日は、誠にありがとうございました。
通夜閉式の挨拶例(エピソードあり)
- 本日は、雨の中、通夜にお越しいただき、心より感謝申し上げます。
私は〇〇の長男、△△と申します。 父は10年前から心臓の病を抱えていました。
しかし、その中でも家族のため、仕事のために頑張り続けてくれました。
彼の趣味は釣りで、私たち家族とよく海に行って楽しんでいました。
彼の会社の同僚や友人たちとは、釣りの話で盛り上がり、「次回の大物を釣るための秘策」を語り合っていました。
別室にて、軽いお食事をご用意しております。
父の楽しかった釣りの話など、お話しいただけると嬉しいです。
告別式は、明日、〇時よりこちらで行います。
本日は、誠にありがとうございました。 - 本日は、寒い中、通夜に参列していただき、感謝の気持ちでいっぱいです。
私は〇〇の娘、△△と申します。
母は、長い間、糖尿病と闘っておりましたが、その中でも家族を支え続けてくれました。 彼女は、私たちが子供の頃、毎週末に手作りのお菓子を作ってくれました。
近所の子供たちも、母のお菓子が大好きで、「次は何を作ってくれるの?」といつも楽しみにしていました。 別室にて、お茶とお菓子をご用意しております。
母のお菓子の思い出話など、お聞かせいただけると幸いです。
告別式は、明日、〇時よりこちらで行います。
本日は、誠にありがとうございました。 - 本日は、風の強い中、通夜にお越しいただき、感謝しております。
私は〇〇の弟、△△と申します。
兄は、若い頃から絵を描くのが好きで、多くの展示会にも参加していました。
彼の作品は、色鮮やかで、見る人の心を癒してくれるものばかりでした。
アートスクールの友人たちとは、絵の技法や新しいアイディアについて熱く語り合っていました。 別室にて、お茶をご用意しております。
兄の絵の思い出話など、お話しいただけると嬉しいです。
告別式は、明日、〇時よりこちらで行います。 本日は、誠にありがとうございました。 - 本日は、遠方より通夜に参列していただき、心から感謝申し上げます。
私は〇〇の妹、△△と申します。
姉は、子供の頃から音楽が大好きで、高校・大学と吹奏楽部に所属していました。
彼女のフルートの音色は、聴く人を魅了していました。
音楽学校の友人たちとは、新しい楽曲の練習やコンサートの計画を立てていました。
別室にて、軽いお食事をご用意しております。
姉の音楽の思い出話など、お聞かせいただけると幸いです。
告別式は、明日、〇時よりこちらで行います。
本日は、誠にありがとうございました。 - 本日は、お忙しい中、通夜にお越しいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。
私は〇〇の孫、△△と申します。
祖父は、私が小さい頃から、よく山に登るのが好きで、私もよく一緒に連れて行ってもらいました。
彼の山登りの話は、家族の間でよく語り草になっていました。
山岳会の仲間たちとは、次の山登りの計画を立てたり、過去の冒険を振り返っていました。
別室にて、心ばかりのお食事をご用意しております。
祖父の山登りの思い出話など、お話しいただけると嬉しいです。
告別式は、明日、〇時よりこちらで行います。
本日は、誠にありがとうございました。
通夜振る舞いの開式の挨拶例
- こちらで心ばかりのおもてなしをご用意いたしました。 どうぞご賞味ください。 故人との温かい思い出話で、和やかな時間をお過ごしいただければ幸いです。
- お腹も空いていることと思います。 こちらで少しのお食事をご用意しておりますので、どうぞお気軽にお召し上がりください。 故人の楽しかったエピソードなどを共有しながら、心温まるひと時をお過ごしいただけたらと思います。
- 皆様には長時間お待ちいただき、ありがとうございます。 こちらで軽いお食事をご用意しておりますので、どうぞお楽しみください。 故人との美しい瞬間や思い出を語り合いながら、心の中で彼を偲んでいただければ幸いです。
- こちらで少しだけのおもてなしを準備いたしました。 どうぞご自由にお召し上がりください。 故人との貴重な思い出や、笑顔溢れるエピソードを共有しながら、温かな時間を持っていただけたらと願っております。
- 皆様のお口に合うかどうかわかりませんが、こちらで軽食をご用意しております。 どうぞ遠慮なくお召し上がりください。 故人と過ごした楽しい日々の話で、心温まるひと時を作っていただければと存じます。
通夜振る舞いの閉式の挨拶例
- 皆様、遅い時間までお付き合いいただき、心から感謝申し上げます。 明日、1月15日の〇時より、こちらの斎場で葬儀・告別式を執り行います。 お時間の許す範囲で、故◯◯への最後のお別れをいただけると幸いでございます。 本日は、故人を偲ぶ多くのお話を聞かせていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。 皆様との深い絆を感じることができました。 しかし、時間が遅くなりましたので、こちらでのおもてなしはこれにて終了とさせていただきます。 明日の葬儀・告別式にも、どうぞよろしくお願い申し上げます。
- 皆様、深夜までお付き合いいただき、心より感謝しております。 明日、1月15日の〇時に、この斎場で葬儀・告別式を行います。 ご都合がよろしければ、最後のお別れの場にご参列いただけるとありがたく存じます。 本日は、故◯◯のために多くの方々が集まり、温かいお言葉をいただきました。 そのご厚情に心から感謝申し上げます。 しかし、時間が進んで参りましたので、今宵の集いはこれにて閉じさせていただきます。 明日の葬儀・告別式にて、再び皆様とお会いできることを楽しみにしております。
- 皆様、長時間のご参列、誠にありがとうございました。 明日、1月15日の〇時から、当斎場で葬儀・告別式を予定しております。 お時間が許される方は、故◯◯の最後の旅立ちを見送っていただけると幸いです。 本日は、故人の思い出の話や、皆様からの温かい言葉に心を打たれました。 そのご厚情に深く感謝いたします。 しかし、夜が更けてきましたので、今宵の集まりはこれにて終了とさせていただきます。 明日の葬儀・告別式で、再度皆様と共に故人を偲びたいと思います。
- 皆様方、深夜までのご参列、心からの感謝を申し上げます。 明日、1月15日の〇時に、この斎場で葬儀・告別式を開催いたします。 故◯◯への最後のお別れの場となりますので、お時間がございましたら、ぜひご参列ください。 本日は、故人の生前のエピソードや、皆様の温かい言葉に触れることができ、大変感慨深いものとなりました。 そのすべてに感謝の気持ちでいっぱいです。 時間が遅くなりましたので、今宵のおもてなしはこれにて終了とさせていただきます。 明日の葬儀・告別式で、再び皆様と共に故人を偲ぶ時間を持ちたいと思います。
- 皆様、遅くまでのご参列、誠にありがとうございました。 明日、1月15日の〇時より、こちらの斎場にて葬儀・告別式を執り行います。 故◯◯の最後の旅立ちを、皆様と共に見届けたいと存じます。 本日は、故人の思い出や、皆様からの温かい言葉を共有することができ、心より感謝しております。 しかし、時間が進んで参りましたので、今宵の集いはこれにてお開きとさせていただきます。 明日の葬儀・告別式にて、再度皆様と共に故人を偲びたく存じます。
告別式の出棺時の挨拶例
- 故〇〇の告別式に足を運んでいただき、心より感謝申し上げます。 私は〇〇の長男△△と申します。 故人は昨年、病魔との闘いを始め、家族とともに治療を続けて参りましたが、〇月〇日に安らかにこの世を去りました。 皆様からの温かい励ましや支えに、家族一同、感謝の気持ちでいっぱいです。 故人の遺志を継ぎ、家族として前を向いて歩んで参ります。 今後も変わらぬご支援、ご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。 本日は、誠にありがとうございました。
- 本日は、故〇〇の告別式にご参列いただき、心からの感謝を申し上げます。 私は〇〇の妻、△△と申します。 故人は昨年、突如として病に倒れ、治療を続けてきましたが、〇月〇日に天に召されました。 皆様からの温かい言葉や励ましに、家族一同、故人もきっと喜んでいることと思います。 これからも家族として、故人の思いを胸に、前進して参ります。 今後も変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。 本日は、誠にありがとうございました。
- 故〇〇の告別式にお足を運んでいただき、深く感謝申し上げます。 私は〇〇の次男△△と申します。 故人は昨年、突然の病に見舞われ、家族とともに治療の日々を送っておりましたが、〇月〇日に永眠いたしました。 皆様からの多大なる支えや励ましに、家族一同、感謝の気持ちでいっぱいです。 故人の願いを叶えるため、家族として努力して参ります。 今後も変わらぬご厚情を賜りますよう、お願い申し上げます。 本日は、誠にありがとうございました。
- 本日は、故〇〇の告別式にご参列くださり、心より感謝申し上げます。 私は〇〇の娘、△△と申します。 故人は昨年、病により闘病生活を送っておりましたが、〇月〇日にこの世を去りました。 皆様からの温かい励ましや支えに、家族一同、感謝の気持ちでいっぱいです。 故人の遺志を継ぎ、家族として支え合いながら生きて参ります。 今後も変わらぬご支援、ご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。 本日は、誠にありがとうございました。
- 故〇〇の告別式にご参列いただき、深く感謝申し上げます。 私は〇〇の孫、△△と申します。 故人は昨年、病により闘病生活を始め、家族とともに治療を続けてきましたが、〇月〇日に天に召されました。 皆様からの温かい言葉や励ましに、家族一同、感謝の気持ちでいっぱいです。 故人の願いや思いを胸に、家族として努力して参ります。 今後も変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。 本日は、誠にありがとうございました。
精進落としの開式の挨拶例
- 本日は、故〇〇のためにお集まりいただき、心より感謝申し上げます。おかげさまで、葬儀と火葬が無事に執り行われました。 皆様の温かいご支援に心から感謝いたします。 故人を偲ぶ気持ちを込めて、お料理をご用意いたしました。 どうぞ、お楽しみいただきながら、故人の思い出を語り合っていただければと思います。
- 皆様のご協力のもと、故〇〇の葬儀と火葬が無事に終わりました。 本日は、誠にありがとうございました。 皆様の深いご厚情に感謝申し上げます。 故人を偲ぶ時間として、お料理をご用意させていただきました。 どうぞ、心を込めてお召し上がりください。
- 本日は、故〇〇の葬儀と火葬にご参列いただき、感謝の気持ちでいっぱいです。 皆様のご支援に心から感謝申し上げます。 故人を偲び、感謝の気持ちを込めてお料理をご用意いたしました。 どうぞ、ゆっくりとお楽しみいただきながら、故人の思い出を振り返っていただければ幸いです。
- 皆様の温かいご支援により、故〇〇の葬儀と火葬が滞りなく行われました。 本日は、誠にありがとうございました。 皆様の深いご厚情に感謝申し上げます。 故人を偲ぶ気持ちを込めて、お料理をご用意させていただきました。 どうぞ、心を込めてお召し上がりください。
- 本日は、故〇〇のためにお集まりいただき、深く感謝申し上げます。 おかげさまで、葬儀と火葬が無事に終わりました。 皆様の温かいご支援に心から感謝いたします。 故人を偲ぶ時間として、お料理をご用意させていただきました。 どうぞ、お楽しみいただきながら、故人の思い出を語り合っていただければと思います。
精進落としの閉式の挨拶例
- 皆様のご協力と温かいお気持ちに支えられ、本日の儀式を無事に終えることができました。 故人の思い出をもっと共有したい気持ちは尽きませんが、時間の経過とともに、ここで一旦お開きとさせていただきます。 何か至らない点がございましたら、お許しいただければ幸いです。 本日は誠にありがとうございました。
- 皆様の温かいお言葉とご支援に心より感謝申し上げます。 故人の思い出をもっと深く共有したいところですが、本日はここで一区切りとさせていただきます。 何卒、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 本日はありがとうございました。
- 皆様と共に、故人を偲ぶ時間を持つことができ、大変感謝しております。 もちろん、故人の話はまだまだ尽きませんが、本日はこの辺りでお開きとさせていただきたく存じます。 何か不手際がございましたら、お許し下さい。 本日は誠にありがとうございました。
- 皆様のご協力のもと、本日の儀式を滞りなく終えることができました。 故人の思い出をもっとお話ししたいところですが、本日はここで一旦終了とさせていただきます。 何か至らない点がございましたら、お許しいただければ幸いです。 本日は誠にありがとうございました。
- 皆様の温かいお言葉とご参列に心から感謝申し上げます。 故人の思い出をもっと共有したい気持ちは尽きませんが、時間の制約上、ここでお開きとさせていただきます。 何か不手際や至らない点がございましたら、お許しいただければ幸いです。 本日はありがとうございました。
家族葬での喪主から僧侶へ挨拶を簡単におさらい

家族葬では、喪主から僧侶への挨拶が重要な役割を果たします。 挨拶は、故人との関係や故人への感謝、そして僧侶への敬意を示すためのものです。
僧侶が家族葬の通夜会場に到着した直後、喪主は手短に挨拶を行うことが一般的です。
この際、「会場にご足労いただいた謝意」と「本日はよろしくお願いします」という言葉を添えることが大切です。 通夜終了後、僧侶の控室へ出向き、再度お礼の言葉を述べるのも良いマナーとされています。
また、挨拶の際には、故人との思い出やエピソードを交えることで、より心温まるものとなります。
例えば、「故人は生前、〇〇寺でのお参りをとても楽しみにしておりました。
その思い出を胸に、今日この日を迎えることができました」といった具体的なエピソードを挟むことで、挨拶がより深みを持ちます。
家族葬の挨拶は、故人への感謝と僧侶への敬意を示す大切な時間です。 心を込めて、適切な言葉を選び、挨拶を行うことで、故人の魂を安らかに送り出す手助けと
枕経をお願いする時
- 本日はお忙しい中、お越しいただきまして心より感謝申し上げます。 何卒、ご教示を賜りますようお願い申し上げます。
- 本日はお時間を割いていただき、ありがとうございます。 故人のため、どうぞよろしくお導きをお願い申し上げます。
- お忙しい中、こちらまでお越しいただき、感謝いたします。 故人のため、ご指南のほどお願い申し上げます。
- 本日は特別な時間を割いていただき、ありがとうございます。 故人の魂の安らぎのため、ご教示を賜りますようお願いいたします。
- お忙しい中、故人のためにお越しいただき、心から感謝しております。 どうぞ、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。
告別式で僧侶を迎える時
- 本日はお忙しい中、お越しいただきまして心より感謝申し上げます。 我々は初めての経験でございますので、何卒、ご指南を賜りますようお願い申し上げます。 こちら、お納めくださいますよう。
- この度は、お時間を割いていただき、ありがとうございます。 私たちは不慣れな面が多いので、ご教示いただけますと幸いです。 お心づけとして、こちらをお受け取りください。
- 本日は特別な時間をいただき、感謝いたします。 初めてのことで手探り状態でございますので、ご指導のほどお願い申し上げます。 これを、お納めいただけますと幸いです。
- お忙しい中、故人のためにお越しいただき、心から感謝しております。 不慣れな点も多々ございますので、ご指南を賜りますようお願いいたします。 こちら、お納めくださいますよう。
- この度は、お時間をいただき、誠にありがとうございます。 我々は初めての経験でございますので、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。 こちらを、お受け取りくださいませ。
告別式を終えて僧侶を送る時
- 本日はお忙しい中、故人のために心を込めたお勤めをいただき、心より感謝申し上げます。 お陰様で葬儀を無事に終えることができました。
- この度は、深い敬意をもってお勤めいただき、誠にありがとうございました。 そのお力添えにより、葬儀が滞りなく進められました。
- 本日は、故人のために尽力していただき、感謝の気持ちでいっぱいです。 おかげさまで、葬儀を落ち着いて執り行うことができました。
- 貴重なお時間を割いて、真心を込めたお勤めをいただき、感謝しております。 そのお陰で、葬儀を無事に完了させることができました。
- 本日は、故人に対する深い敬意と共に、お勤めを賜り、誠にありがとうございました。 おかげさまで、葬儀を円滑に進めることができました。
まとめ
家族葬の中で、喪主としての挨拶は非常に重要な役割を果たします。
故人との思い出や、参列者との絆を深めるための言葉を選ぶことで、心温まる挨拶となります。
また、僧侶や参列者への感謝の気持ちを忘れずに伝えることで、故人への敬意を示すことができます。
挨拶の際には、適切な言葉遣いやマナーを心がけることが大切です。
そして、故人や参列者に対して心からの感謝や哀悼の気持ちを伝えることで、告別式をより心に残るものとすることができます。
この記事が故人を感謝とともに送り、参列者との良い時間を過ごすためにお役に立てれば幸いです。